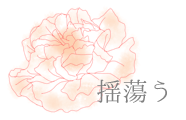|
初めは同じ匂いがした。気怠そうにつまらなそうに日々を過ごしている彼を見て単純に同類だと、そう思ったのだ。でも違った、そんな気にさせられただけだった。あたしには彼ほど欲してるものはなかったし、彼ほど諦めも悪くもなかった。だから簡単に手放せもしたし、懐かしむ事も出来る。だからあたしには過去でしかないそれを美化するには少し熱が足りない。それでも勝手知るその競技は他のどのスポーツより楽しく観戦できる。その中に青峰はいた。コートに迸る熱は彼のフラストレーションそのもので、見ていて驚かされた。 「ねぇ、青峰にはさ試合中のギャラリーの声援って聞こえてるの?」 「は?」 「あたしはさ、聞こえてなかった。もしかしたらコート内の声も」 「いきなり何だよ。つーかお前、バスケやってたのかよ」 「何でバスケって決めつけんのよ」 「それ、バスケやってる奴なら誰でもやる」 「あー、確かに。でもあたしこれ下手なんだよね」 指先でくるくる回るボールの感触は懐かしい光景を思い描かせる。色あせ始めたあの日々は瞼の裏にしか存在しなくて、瞳を閉じなければ出会えない。だけどあの頃より重くなった睫毛が容易にあたしを過去へ連れて行く。このボールの感触はあたしにとって懐かしむものでしかないけれど、目の前のこの男にとっては未来でしかないのだろう。手放せず、抗い、苦悩し、掬い上げられた彼の未来。青峰はヒーローであり続ければいいと思う。 「その恰好でそれやんのかよ。パンツ見えんぞ」 「まー、いいよ。見られても平気な"やつ"だし」 「どういう意味だよ」 「どっちも」 「……うぜ」 股下を通すドリブルは鞠付きの延長のような感覚で、両足を交互に動かしながら何回通せるか、あたしがまだ部活生と呼ばれていた頃よくみんなで競ってた。あの頃は制服のままこんな事するなんてなかったけど。そんなあたしを見る青峰の顔は呆れきってて、まさに凡人を見る目をしてる。そう言えば初めて会った時はもっと酷い視線を向けられ「話しかけんな」と言われた。あれは多分嫌悪からくる視線だったんだろう。見た目や素行、世間で言う派手なグループにいる灰汁の強い類の女。とりまき、ミーハー、女狐、悪女、上げればキリがない程出てくる例えに否定はしない。そんなあたしの口から「部活」について、まして青峰とは切っても切れないバスケに関する話が出て来たのは意外でしかないだろう。 「この前、ウィンターカップだっけ?あれ見に行ったんだよね」 「……」 「青峰、ホント凄いんだね」 「別に、」 「負けたけど」 「ッチ。うるせ!」 「でさ?あの、変なモード入った時って何なの?」 「変なモードって何だよ」 「スーパープレイ連発モード」 夕方の屋上で似合わないセリフを連発するあたしは今、変なモードに入ってるのかもしれない。その証拠に青峰は初めて会ったあの日よりずっと嫌悪感を露わにしている。バスケの話なら相手をしてくれるかもしれない。なんて思ったわけじゃない。ただ、チャンスがあったら聞いてみたいとずっと思っていた事だった。昔、試合中の事で一度だけだけど強烈に覚えている事がある。プレヤーとして凡人だったあたしが何故だかその日の試合中凄く良く動けた事が強烈に記憶に残っているのだ。集中力が凄かったんじゃないかとバスケを辞めた今になって気が付いたわけだけど、この前の青峰の試合を観てあたしの体感したあの感覚はやっぱり凡人、いやそれ以下のものだったんだろうと思った。あれはウィンターカップに出場した選手なら誰でも常にあの状態が大前提なんだろう。この時点で自分の凡庸さに、底の低さにバスケを続けなくて良かったと思った。 「ゾーンってのだよ」 「ゾーン。へぇー、そんな名前なんだ」 「入っちまうと、お前の言う声は聞こえねぇ。多分な」 「多分って、何それ」 「プレイ中は他の事は頭にねぇんだよ」 「そっかー、さぞかし気持ちいいだろうね。それ」 「……」 青峰はあたしが向ける羨望の眼差しに先ほどまで嫌悪感むき出しだったその表情を和らげた。何かに集中して気持ちよくなるなんて、もうずっと体感してないあたしにはそれを説明出来る青峰が羨ましい。ゾーンと言う名の踏み込めないその絶対領域は尚の事。だから未知の領域を易々と言葉に出来てしまう青峰はやっぱり天才と呼ばれるのだろう。そこにたどり着かなければ、たどり着けなければ言えない言葉だ。 「で?お前は毎回聞こえなかったのかよ」 「うん。誰かの声援が聞こえた事はない」 「応援されなかったんじゃねーの?」 「それはない。ベンチの応援にスタメン全員の名前呼ぶのあったもん」 「ベンチの声も聞こえねぇって、監督の声もかよ」 「それがさー、監督の激はすんごい聞こえてたんだよね。……多分」 「……、ただ単に覚えてねぇだけだろそれ」 「んー、それか自己中にみんなの事無視して動き回ってたのかも」 「あ?そりゃ嫌味か?」 「まさか。あたしが"青峰みたい"に活躍できるわけないし」 だからまた見せてよ。なんて口にしそうになった自分に只ならぬ違和感を感じる。やっぱり変なモードに入っているのかもしれない。いつもより饒舌な自分、いつも生返事だった青峰が今日はよく答えてくれるからそれは余計で、掌に感じるバスケットボールの感触はそのスイッチかもしれない。あたしより青峰の方がこれは似合うのだからとワンバウンドさせボールを彼に渡した。それを片手で受け止め左右にドリブルする青峰の姿は思っていた以上に様になっていて、予想以上の光景に思わず笑ってしまう。なんなの?カッコ良すぎ。そう零すと彼は小さく、小さく笑った。 「」 「ん?」 「らしくねぇな」 「……だよねー。自分でもそう思う」 左右に動くボールと青峰の手は揺蕩う揺れる。左右に揺られ緩いリズムを奏でるボールの音が心地いい。まるで花占いをするかのように彼の揺らすボールの行方に違和感の答えを委ねてみたけれどボールは彼の手の中、揺れるだけ。夕暮れの屋上、伸びる影、鳴り響くボールの音、見据えた先の男は奇跡を背負ったヒーローで、多分、あたしの好きな人。
|